はじめに
前回の記事では、廃棄物処理法における「廃棄物」の定義を確認し、その中で「不要物」という言葉が核心であることを紹介しました。
👉 廃棄物処理法における「廃棄物」の定義をわかりやすく解説
実務では、「これは廃棄物か? それとも有価物か?」という判断が、企業活動に直結します。廃棄物とされれば、収集運搬や処分に関して厳しい規制が課され、違反すれば刑事責任や行政処分につながりかねません。
この記事では、判例で確立された総合判断説を整理したうえで、特に実務上重要な④取引価値と⑤事業者の意思について、環境省通知や裁判例を交えながら解説します。
総合判断説
「不要物」該当性を判断する基本枠組みは、最高裁平成11年3月10日判決(いわゆるおから決定)で示されました。
最高裁は次のように述べています。
- 「不要物」とは、自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいう。
- 該当性は次の要素を総合的に考慮して判断する。
- その物の性状
- 排出の状況
- 通常の取扱い形態
- 取引価値の有無
- 事業者の意思
つまり、一つの要素だけで決まるのではなく、社会通念上「不要」といえるかを全体として判断する、これが総合判断説です。
環境省通知について
判例の枠組みは環境省の通知等を通じて整理され、現在は2018年改正版「行政処分の指針について」(廃棄物規制課長通知)にまとめられています。
廃棄物該当性については、第1の4(2)(3~5頁)にて廃棄物の解釈に関する詳細な指針が示されており、実務上、参照が不可欠です。
👉 環境省通知はこちら
以下では、この通知や裁判例を踏まえ、事実認定上重要なポイントとなる、④取引価値と⑤事業者の意思について具体的に見ていきます。
④取引価値の有無
基本的な考え方
市場で有償で取引される場合、不要物該当性を否定する方向に働きます。
しかし、名目的な売買や単発の取引では足りず、継続的に社会的な再利用スキームが確立しているかどうかが重視されます。
- 有償取引が成立すれば「有価物」として扱われやすい。
- 逆に「処理費用を払って引き取ってもらう」場合や、形式的に有償でも実態は処理費用負担が上回る(逆有償)の場合は、廃棄物と評価されやすい。
- 通知でも「再利用が社会的に確立しているか否か」を判断基準として強調しています。
裁判例の評価
- おから事件(最決平成11年3月10日)
豆腐製造業者によって大量に排出される「おから」について、食用として有償で取引されるわずかな量を除く、大部分は牧畜業者等に無償で引渡しするか、有償で処理を委託していたことを重要な要素として、当該おからが産業廃棄物であるとした原判決を維持した。 - 木くず事件(東京高判平成20年4月24日)
木くずがチップ化され、製造事業として継続的に再生利用されていたケースで、廃棄物該当性を否定するためには原則として有償で譲渡できることを要するとしつつ、再生利用が製造事業として確立したものであり継続して行われている場合には廃棄物処理法の規制を及ぼす必要がないとの判断を示した。当該判決では、再生利用目的があったとしても、事業として確立し継続したものとはなっていなかったため、廃棄物該当性を否定する理由にはならないとの結論であった。
実務上のチェックポイント
- 単発の売買ではなく、継続的な市場取引か?
- 引取先が実際に利用しているか、それとも「処理」しているだけか?
- 処理費用を負担していないか?
- 再利用のスキームが社会的に確立・継続しているか?
⑤事業者の意思
基本的な考え方
事業者が「まだ使うつもりだった」と主張しても、それだけでは不十分です。
通知では、⑤事業者の意思は客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る意思であるとされます。
つまり、占有者の主観的な認識は決定的な要素ではなく、実際に利用可能か、合理的な裏付けがあるかで判断されます。
通知のポイント
- 単に「利用予定」と主張するだけでは廃棄物否定の根拠にはならない。
- 実際に利用可能な態様が存在し、社会通念上合理的に裏付けられている必要がある。
- 性状や取引価値等の他の要素とあわせて、客観的に判断される。
実務上のチェックポイント
- 利用計画は具体的か?(数量・用途・期間が明確か)
- 第三者から見ても合理的に利用可能といえるか?
- 実際に過去の利用実績があるか?
- 単なる「気持ち」ではなく、客観的証拠(契約、取引記録等)で裏付けられるか?
実務的示唆・まとめ
- 廃棄物該当性は、総合判断説が基本。
- 実務では、裁判例や通知を通じて客観的な基準が整備されている。
- 特に重要なのは:
- 継続的な再生利用スキームの存在(④取引価値)
- 意思の客観化(⑤事業者意思)
企業がリスクを避けるには、単発の取引や「使うつもり」という口頭の説明では足りません。制度的に裏付けられた利用スキームや客観的証拠を整えておくことが不可欠です。
また、廃棄物か有価物かの線引きは、事案ごとに判断が分かれ得る領域です。迷った場合には、通知や自治体の運用を確認したうえで、弁護士など専門家に早めに相談することを強くおすすめします。

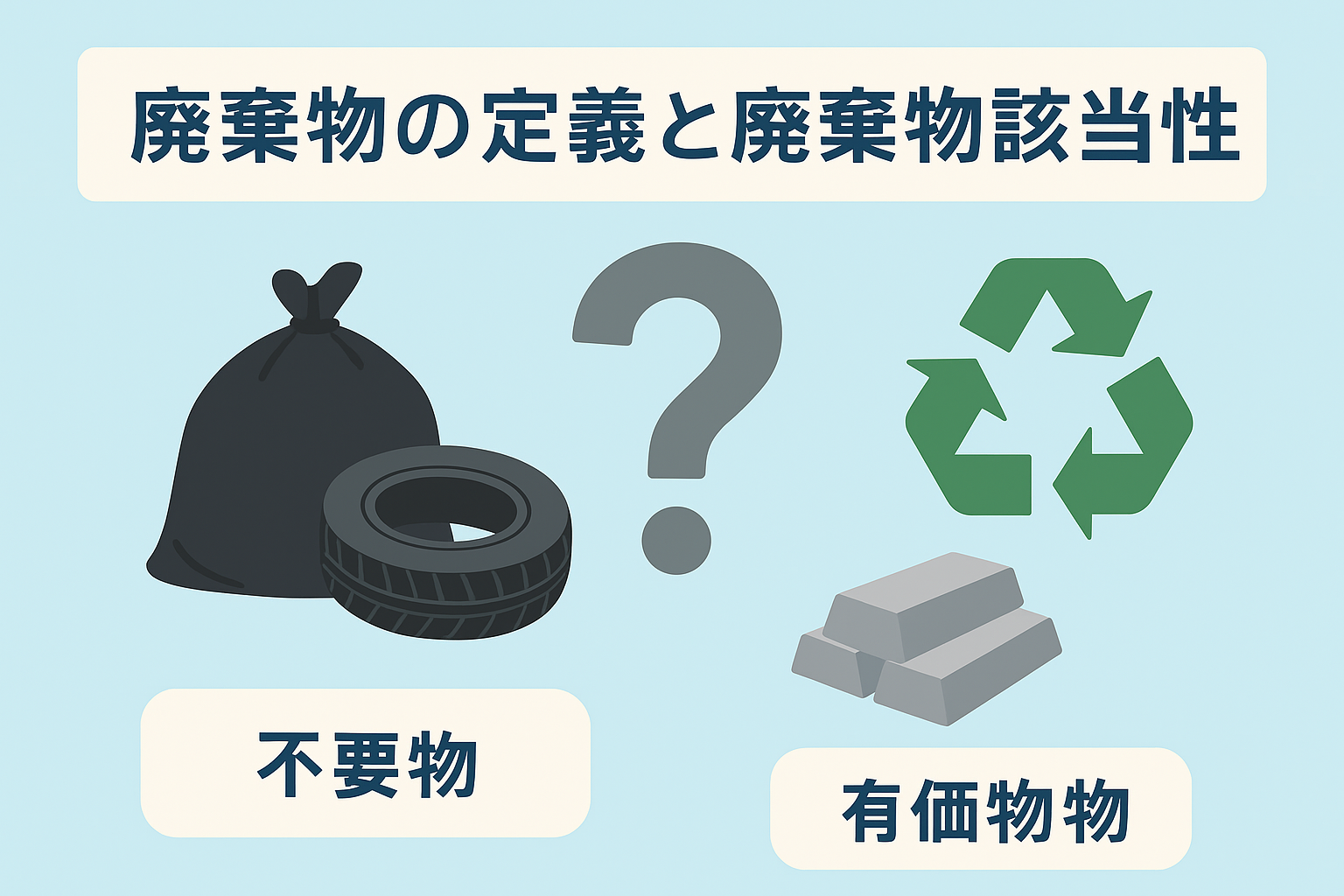
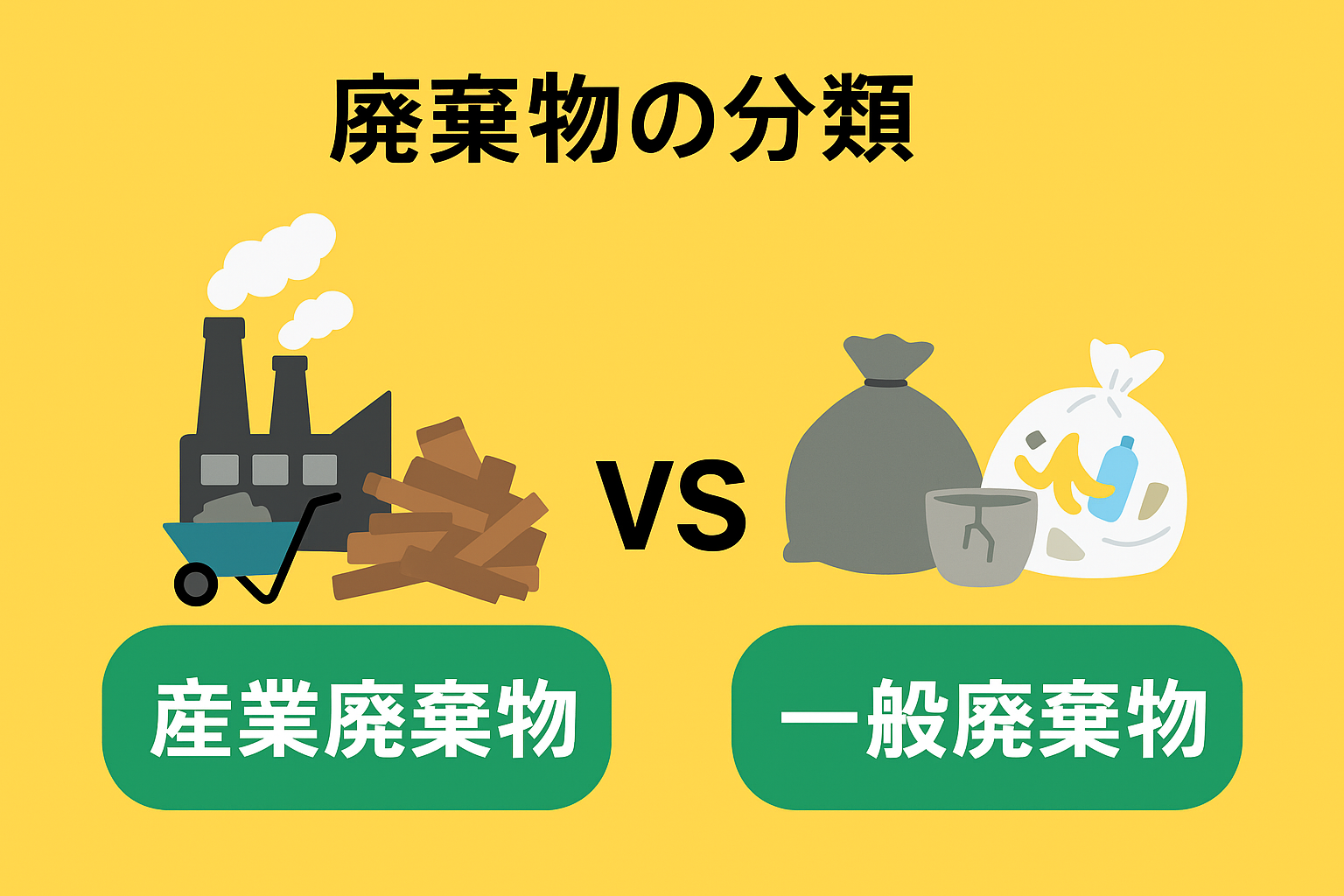
コメント