はじめに
司法試験受験生の皆さん、こんにちは。
このサイトでは、井田良ほか『刑法事例演習教材[第3版]』(有斐閣、2020年)に収録されている全52問について、私が受験生時代に作成した刑法事例演習教材の解答例を順に公開してきました。
第52問「サギの恩返し」は、現住建造物放火罪や過失致死罪、保険金詐取に関する詐欺未遂罪、さらに公務員による加重収賄罪や保険会社職員による背任罪など、複数の犯罪類型が交錯する総合的な事案です。
この解答例では、甲・乙・丙それぞれの行為について、構成要件の充足、因果関係、故意・目的の有無を丁寧に検討し、多重的な論点を一貫した視点で整理することを目指しました。刑法の論点整理に一定の習熟が求められる最終問題として、実力確認に適した素材といえるでしょう。
これをもって、「刑法事例演習教材[第3版]」全52問すべての解答例の掲載が完了となります。読者の皆さんが、各問題の検討を通じて論点把握力や答案構成力を高め、司法試験に向けた学習をより確かなものにしていただければ、これに勝る喜びはありません。
引き続き、刑法の思考の蓄積と実践的理解の深化に努めていってください。
解答例
第1 甲の罪責
1 ガソリンを本件建物の車庫側の外壁に大量に撒布し、新聞紙を棒状に丸めて火をつけ、これを車庫の中に投げ込んだ行為について現住建造物放火罪(108条)が成立するか。
(1)「住居」とは、人の起臥寝食の場所として日常使用されるものをいうところ、本件建物は、甲が所有し、妻Bと2人で住んでいるから「住居」にあたる。
(2)「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいう。ガソリンは引火性が高い物質であるから、これを撒布すること自体焼損の危険を有する。そして、甲は、大量のガソリンを撒布した上で、火をつけているから、焼損の危険がある。したがって、「放火」にあたる。
(3)「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立して燃焼を継続することをいうところ、本件建物は全焼しているから、「焼損」にあたる。
(4)甲は、上記事実を認識しているから、故意(38条1項本文)が認められる。
(5)よって、現住建造物放火罪(108条)が成立する。
2 同行為についてBに対する過失致死罪(210条)が成立するか。
(1)甲は、Bに危害が及ばないようにBが確実に不在の時を見計らって、放火を行うことにしている。そして、Bが同窓会に出席するために外出し、夜まで帰宅しない予定であることを確認している。そのため、Bの死亡結果を認識認容していないから、殺意(38条1項本文)は認められない。
(2)「過失」とは、予見可能性を前提とする結果回避義務違反をいう。
Bは、火災が起こる少し前に、何も知らず忘れ物を取りに自宅に戻っていた。甲は、Bに危害が及ばないように計画を立てていたにもかかわらず、放火の直前にBが本件建物にいないことを確認していないから、結果回避義務違反が認められる。したがって、甲には「過失」がある。
(3)Bは「死亡」している。
(4)よって、過失致死罪(210条)が成立する。
3 謝礼の趣旨で、乙の銀行口座に200万円を振り込んだ行為について贈賄罪(198条)が成立する。
4 C社に対し火災保険金の支払方を請求した行為について詐欺罪(246条1項)が成立するか。
(1)火災保険金は、金銭であるから「財物」にあたる。
(2)「欺いて」とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることである。
甲とC社との間の火災保険契約の約款には、「保険契約者又は被保険者が故意で生じさせた損害には保険金が支払わない」ことが明記されていた。そのため、C社は、保険金請求者に故意がないことに関心を寄せていることが外部的にも明らかである。故意で保険金請求された場合にはC社が損害を被ることになるから、約款には合理性が認められる。そうすると、支払決定の権限を有する業務部長Dは、甲が故意で放火を行ったとすれば、保険金の振込みを行わないといえる。
したがって、「欺いて」にあたる。
(2)Dは、正しい請求であると誤信して決裁を行い、その結果、C社から甲名義の銀行口座に、火災保険金名下に3500万円の振り込み入金が行われた。したがって、「交付させた」といえる。
(3)もっとも、C社のサービスセンターの従業員丙は、それが不正請求であることを直ちに見破り、書類の記載の中で疑いが生じそうな部分を補正した。そのため、甲の「欺」く行為の危険が3500万円の移転結果に実現したとはいえないから、因果関係が認められない。
(4)甲は、「欺いて」に該当する事実を認識認容しているから、故意(38条1項本文)が認められる。また、経営の行き詰まりを乗り越えるためには火災保険金を騙し取るほかないと考えているから不法領得の意思が認められる。
(5)よって、甲には詐欺未遂罪(250条、246条1項)が成立する。
5 甲には、①現住建造物放火罪、②過失致死罪、③贈賄罪、④詐欺未遂罪が成立する。①と②は、「1個の行為」であるから、観念的競合(54条1項前段)となる。その他は別個の行為であるから、併合罪(45条前段)となる。
第2 乙の罪責
1 甲が、謝礼の趣旨で乙の銀行口座に200万円を振り込んだ行為について加重収賄罪(197条の3第2項)が成立するか。
(1)乙は、A市警察署の刑事課に所属し、犯罪捜査を担当していた警察官であるから、「公務員」(7条1項)にあたる。
(2)乙は、種々の事情から見て、甲による保険金騙取目当ての放火に間違いないとの心証を抱いたが、他方、甲とは旧知の間柄であり、甲にはひとかたならぬ恩義を感じていたことから、恩返しのため、自動車の故障を原因とする偶発的な事故であったとして本件を処理した。甲は、謝礼の趣旨で乙の銀行口座に200万円を振り込んだところ、乙は直ちにその趣旨を理解し、その金は自宅マンションを購入した際に組んだ住宅ローンの返済の一部に充てた。そのため、本件の対価として200万円が支払われたといえるから、「賄賂を収受」したといえる。
(3)「職務」とは、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務をいう。
賄賂を収受した時点で、乙は、県警から警視庁へ転籍し、刑事局刑事企画課の法令係として、刑事法令の調査や研究に携わっていた。そのため、事故処理は、現在の乙の一般的職務権限に属しない。
もっとも、収賄罪の保護法益は、職務の公正に対する社会一般の信頼にある。転職したとしても、現在公務員である者が賄賂を収受することによって、過去の職務の公正に対する社会一般の信頼が害される。そのため、一般職務権限を異にする他の公務に転職した場合にも、「職務に関し」にあたる[1]。
乙は、犯罪捜査を担当していた警察官として、自動車の故障を原因とする偶発的な事故であったとして本件を処理したことの対価として賄賂を収受している。この時点では、一般的職務権限に属する行為であったから、この対価として賄賂を収受した以上、「職務に関し」にあたる。
(4)以上の対価は、「不正な行為をしたこと」の対価である。
2 よって、乙には、加重収賄罪(197条の3第第2項)が成立する。
第3 丙の罪責
1 書類の記載の中で疑いが生じそうな部分を補正して、その案件をC社で支払決定の権限を有する業務部長Dによる決裁に回した行為について詐欺罪(246条1項)が成立するか。
丙は、恩返しの趣旨で甲に保険金が下りるように手続を進めてやろうと考えている。そのため、上記行為によって、利益を得る意図はないから、不法領得の意思が認められない。
よって、詐欺罪は成立しない。
2 詐欺未遂罪の幇助犯(62条1項、250条、246条1項)は成立するか。
(1)「幇助」とは、実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいう。
丙は、書類の記載の中で疑いを生じそうな部分を補正してる。丙は、C社の従業員であり、保険金請求の事案を多く処理しているから、疑いを生じそうな部分を認識できる。そのため、丙が補正を行うことによって、決裁者が発覚することを防ぐことができるから、詐欺を容易にしたといえる。
(2)丙は、そのまま手続を進めれば、C社に3000万以上の損害が生じるであろうことをはっきりと認識しているから、故意(38条1項本文)が認められる。
(3)よって、詐欺未遂罪の幇助犯(62条1項、250条、246条1項)が成立する。
3 同行為について背任罪(247条)が成立するか。
(1)丙は、C社のサービスセンターの従業員であるから、C社との委託信任関係に基づきDの保険金請求の決裁を補助している。そのため、「他人のためにその事務を処理する者」にあたる。
(2)火災保険契約の約款には、「故意で生じさせた損害に対しては保険金が支払わない」ことが明記されていたから、不正請求であることを見破りながら補正することは、「任務に背く行為」といえる。
(3)丙は、恩返しの趣旨で甲に保険金が下りるように手続きを進めてやろうと考えているから、「第三者の利益を図る目的」が認められる。
(4)C社は、甲名義の銀行口座に、火災保険金名下に3500万円の振り込み入金が行われ、C社の全体財産が減少しているから、「財産上の損害」が生じている。
(5)よって、背任罪(247条)が成立する。
4 丙には、詐欺未遂罪の幇助犯と背任罪が成立する、両者は、「1個の行為」であるから、観念的競合(54条1項前段)となる。
参考判例
[1] 県職員住宅供給公社出向事件(最決昭和58・3・25刑集37巻2号170頁)。


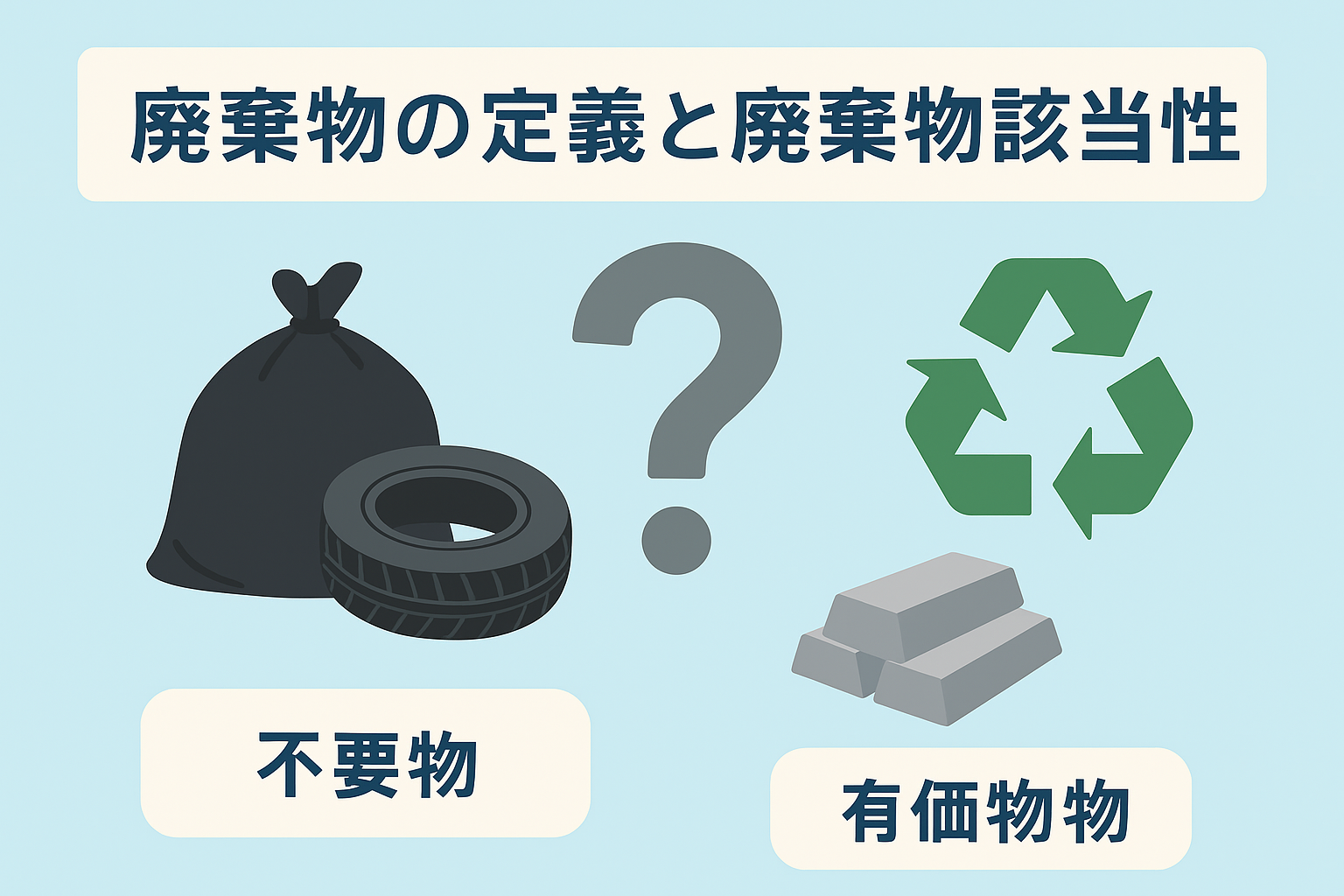
コメント