はじめに
廃棄物処理法(正式名称「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)は、産業廃棄物の処理について「誰が責任を負うのか」「どのように処理するのか」を細かく定めています。
産業廃棄物を出す事業者は、最終処分まで一貫して管理責任を負う点が最大の特徴です。
本記事では、排出事業者の立場から、委託処理のルールやマニフェスト制度を中心に、実務上押さえるべきポイントを解説します。
👉 廃棄物の定義についてはこちら
👉 廃棄物該当性の判断枠組みについてはこちら
👉 産業廃棄物の種類と分類についてはこちら
排出事業者に課される基本的義務
自ら処理の原則
排出事業者は、自らが産業廃棄物を処理することが原則とされています(法11条1項)。また、処理を行う場合には、法律や施行規則に定められた基準(処理基準と呼ばれます。)に従わなければなりません(法12条1項)。
実務上は、ほとんどの事業者が自ら処理を行わず、許可業者に委託しています。
委託処理のルール
委託処理を行う場合でも、排出事業者の責任は免れません。委託時には次のルールが設けられています。
- 委託可能な相手の限定
処理を委託できるのは、産業廃棄物運搬業・産業廃棄物処分業の許可を持つ者に限られます(法12条5項)。許可は品目ごとに与えられるため、対象の産業廃棄物に応じた許可を確認する必要があります。 - 書面契約の義務
委託契約は必ず「書面」で結ぶ必要があります(法12条の6・施行令6条の2第4号)。契約書には法定の記載事項があり、施行令・施行規則に基づく添付書類も必要です。 - 二者間契約の必要性
排出事業者は、運搬業者と処分業者それぞれと契約しなければなりません。一方のみとの契約では不十分です。 - マニフェストの交付
排出事業者は、運搬・処分を委託する際にマニフェスト(管理票)を交付し、最終処分までの過程を確認する義務があります(法12条の3)。
マニフェスト制度と管理体制
制度の仕組み
マニフェスト制度は、委託した廃棄物の流れを追跡・管理する仕組みです。
排出事業者は、運搬又は処分時にマニフェストを交付(法12条の3第1項)したうえで処理報告を受け取り、最終処分まで確認しなければなりません(法12条の3第6項)。
一定期間(90日または180日)以内に報告が返ってこない場合や、不備・虚偽がある場合には、処理状況を確認し、必要に応じて都道府県知事に報告する必要があります(法12条の3第8項・施行規則8条の28)。
電子マニフェストの普及と義務化
従来は紙マニフェストが中心でしたが、現在では電子マニフェストの利用が広がっています。多量の特別管理産業廃棄物を生ずる一定の事業者には、電子マニフェストの利用が義務付けられています(法12条の5第1項、施行規則8条の31の2・31の3)。もっとも、この義務は一部の事業者に限られており、その他の事業者は任意で利用することが可能です(法12条の5第2項)。
電子マニフェストを任意利用する場合でも、事務作業の効率化や返送状況のリアルタイム確認といったメリットがあります。そのため、義務化対象外の事業者であっても、導入を検討する意義があります。
実務上のチェックポイントとリスク管理
排出事業者が最低限押さえるべき実務対応は次のとおりです。
- 委託先の許可状況の確認
契約前に、対象廃棄物の品目・処理方法について適切な許可を持っているかを必ずチェックする。 - 契約書の整備と定期見直し
法定記載事項が網羅されているか、契約期間が切れていないかを確認する。 - マニフェストの管理体制
返送期限内に届いているか、不備がないかを社内で継続的にモニタリングする。
これらの対応を怠った場合、排出事業者は行政処分(改善命令・許可取消等)や刑事罰の対象となり得ます。また、都道府県による指導・勧告も行われるのが実務上の運用です。ルールの理解だけでなく、運用の徹底がリスク回避の鍵となります。
まとめ
排出事業者は、委託処理をした場合でも最終処分まで一貫して責任を負うことが法律上明確に定められています。そのため、
- 委託契約の適正化
- マニフェストによる追跡管理
- 特別管理産業廃棄物への慎重な対応
- 違反時に科される行政処分・刑事罰のリスクへの理解
を押さえておくことが不可欠です。これらを怠れば、法的責任に直結するだけでなく、企業の信用失墜にもつながります。

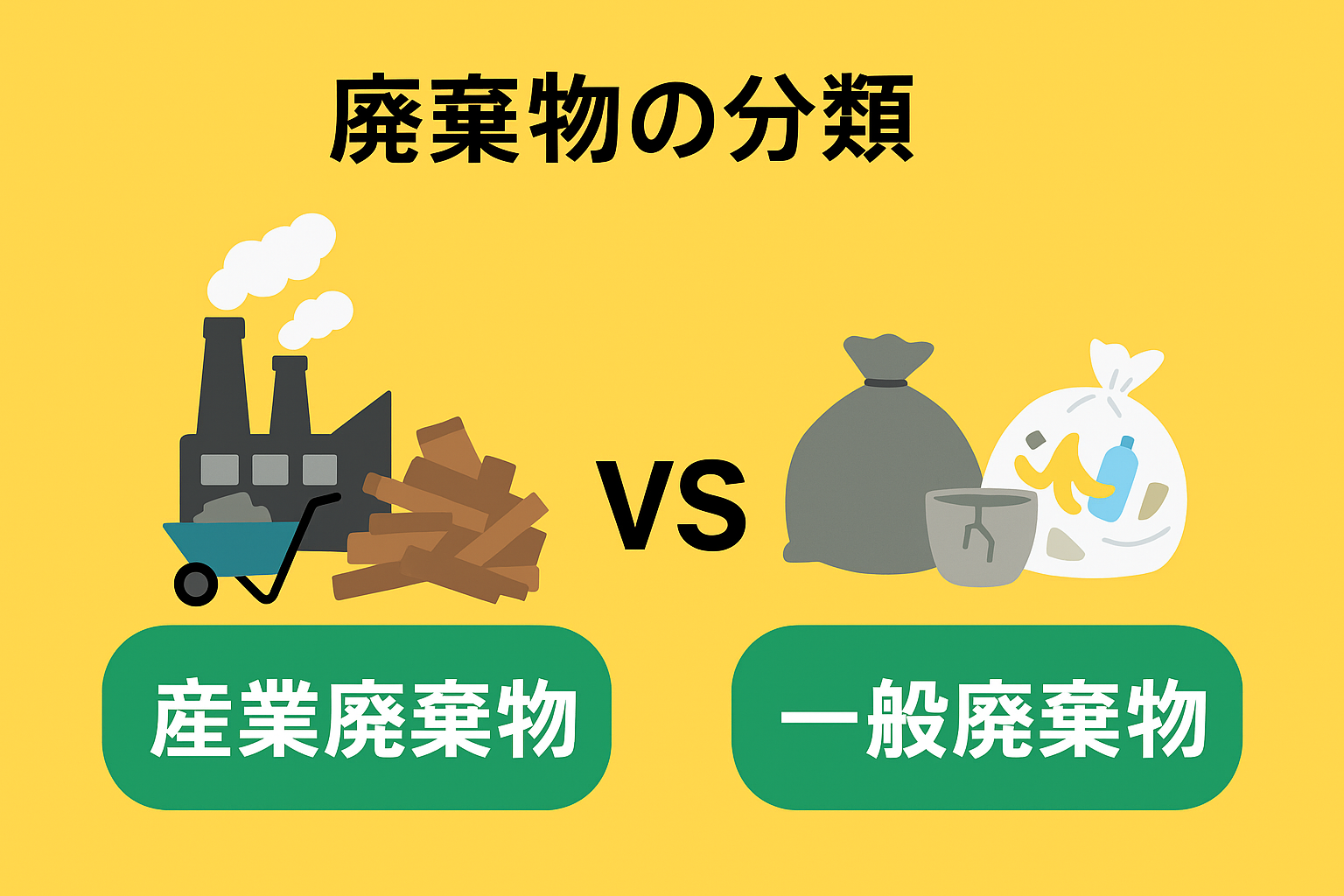

コメント